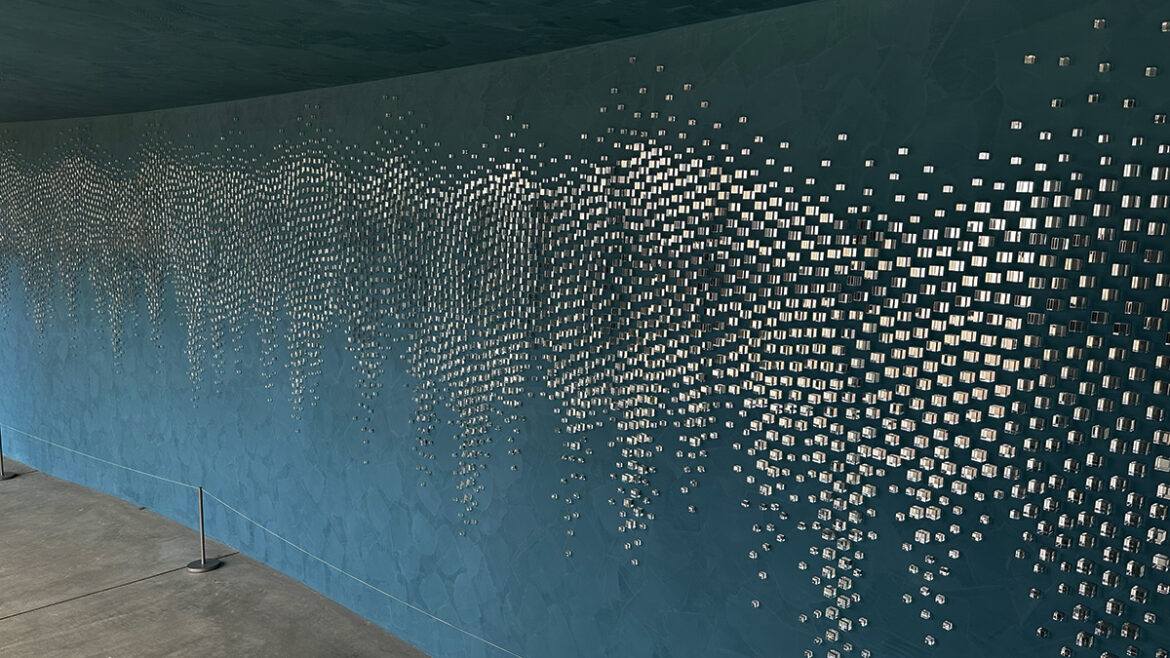イーストマン・コダックが深刻な存続危機に直面していると報道されている。2025年8月、第2四半期の業績を発表し、約5億ドルの債務返済資金が不足しているとして廃業の可能性を会社が示唆している。
133年にわたって写真業界を牽引してきたコダックが、無くなるかもしれない。TRY-XやT-MAXを使い続けているが、もはや手に入らないかもしれないと思うと残念だ。
コダックは1888年の創業以来、写真文化の発展に中心的な役割を果たしてきた。1981年には売上が100億ドルに達し、最盛期には6万人を超える従業員を抱える世界的企業として君臨していた。この成功の背景には、カメラ本体ではなく消耗品であるフィルムで利益を上げる「替カミソリ刃戦略」があった。むしろ、写真が普及するとカメラ本体を製造する企業が雨後の筍のように増えて、コダックは、その戦略さえ意識していなかったかもしれない。
コダックの苦境の原因は、事業の中心をフィルムからデジタルへ移行できなかったことにある。皮肉なことに、コダック自身が1975年に世界初のデジタルカメラを開発した。1990年頃に担当していたニューヨーク郊外で行われていたゴルフトーナメントの会場で、ニコンをベースに使ったコダックのデジタルカメラを見たことがあった。しかし、フィルム事業での大きな成功が、デジタル化への適応を阻害する要因となった。同社は既存のフィルム事業に悪影響を与えることを恐れ、デジタルカメラの商業化を見送るという致命的な判断を下したのだ。
2000年代に入ると、デジタルカメラの普及とともにフィルム市場は急激に縮小した。200万画素を超えるデジタルカメラが登場すると、フィルム写真に匹敵する画質が得られるようになり、写真業界は完全にデジタルへと移行していった。
この写真のデジタル化は、写真の本質的な価値を根本から変えた。フィルム時代の写真は貴重なものであり、1枚1枚に希少性があった。現像するまで写真の出来がわからないドキドキ感、フィルムの残数を気にしながらシャッターを切る慎重さ、これらすべてが写真文化の重要な要素だった。
しかし、デジタル化により写真は無限に複製可能な情報となった。シャッターを押せば即座に確認でき、不要なら削除できる。この変化は写真の希少性を失わせ、代わりに即時性と可搬性を重視する文化を生み出した。写真から単なる画像に変わった。
写メが登場して写真は一層日常化した。そして、スマホとSNSの普及により、写真はさらに劇的な変化を遂げた。2007年のiPhone登場以降、写真撮影は記録から発信の手段へと変貌した。InstagramなどのSNSが提供する「いいね」や「シェア」システムは、写真に新たな価値基準をもたらした。それは、「思い出を残すため」から「誰かに見せるため」「共感してもらうため」の撮影へと目的が変化したことだ。
最近は、メモを取る代わりに、印刷物であれデバイスのスクリーンであれ写真でメモを取る。写真は軽くなったのだろう。
コダックの苦境は、企業の栄枯盛衰を超えて、フィルム時代の終焉を象徴する出来事である。学ぶべき教訓は、過去の成功体験に固執することの危険性と、変化への適応力の重要性である。富士フィルムが、フィルム技術を生かして化粧品に参入したように多角化戦略で成功を続けている一方、コダックが苦境に陥った対照的な運命は、企業戦略の違いが生む結果の大きさを物語っている。